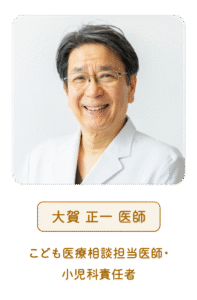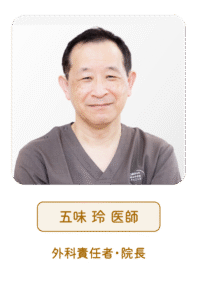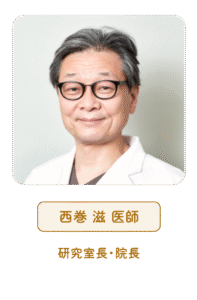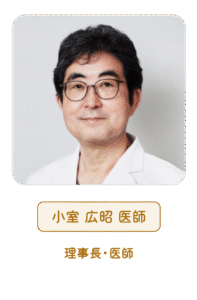③頭のゆがみは0歳からケアする時代へ——正確な診断と適正なヘルメット治療とは
0歳からの頭のかたちクリニックの要職者4名の座談会の様子を全4編にわたって配信します。0歳からの頭のかたちクリニックにはどういう特徴があるのか、中で働いている先生方がどのような考えをもってやっているのかなど是非、0歳からの頭のかたちクリニックをご理解いただく一助にしていただけると嬉しいです。 登場する先生方は以下の4名です。
 0歳児からの頭のかたちクリニックで日々診療にあたる医師にお集まりいただき、それぞれの専門的視点から治療やクリニックの取り組みについて伺うインタビュー。第3回目となる今回は、診療の流れや治療に採用しているヘルメット「クルムフィット」のこと、レントゲン撮影を行う目的や安全面について話を聞きました。
0歳児からの頭のかたちクリニックで日々診療にあたる医師にお集まりいただき、それぞれの専門的視点から治療やクリニックの取り組みについて伺うインタビュー。第3回目となる今回は、診療の流れや治療に採用しているヘルメット「クルムフィット」のこと、レントゲン撮影を行う目的や安全面について話を聞きました。

──実際の診療の流れについて教えてください。
小室:まず問診票で情報を得て、頭部全体を一瞬で撮影できる3Dスキャナー機器を利用して、頭の形状を計測・解析します。そのデータができた時点でどの辺りの変形が気になるかを親御さんに伺い、視診と触診に進みます。その後、実際にデータを見ながら形についてお話しして、最終的にはきちっと評価した数字を元に、クリニックのガイドラインに沿って適用があればヘルメット治療の原理をご説明します。必要な場合はヘルメット治療をお勧めしますが、ヘルメットは作るのに2週間かかるため、初回診療後の1週間以内にお返事をいただくようにしています。今はオンラインでお申し込みもできるので、曜日に関係なく休診日でもお申し込みいただけますし、一度家に帰ってご家族で検討してご自宅からお申し込みをいただくことも可能です。
──クリニックでは、数あるメーカーの中からジャパン・メディカル・カンパニー社のヘルメット、クルムフィットを採用しています。これらを選ばれた理由は?

五味:ヘルメットは90年代くらいからアメリカでよく作られるようになってきて、日本でも2000年代から2010年頃まではそれを輸入して使っていました。ただ、それらの製品はクルムシリーズよりももっと重くて中が硬いタイプだったんですね。そこからいくつかの工夫を経て、ジャパン・メディカル・カンパニー社のアイメットが誕生しました。日本人向けということを考慮して、軽く、それから通気性を良くしてこのジメジメとした湿気の多い日本でも使えるようにしていますが、実は初期のヘルメットはクッションの取り替えができず、汗をかいて臭うこともありました。その中でクッションの取り替えができる、自分で洗えるということを1つの目標にして、貼り替えが簡単にできるクルムができたという経緯があります。その後、私も医師として開発に協力をして一世代前のクルムのクッション、そしてその前の初代モデルのアイメットのクッションのいいとこ取りを試み、その2つをミックスしたような形でクルムフィットが生まれました。 クルムシリーズの良いところは、軽い、通気性が非常に良い、クッションのバリエーションがあるという3点です。クッションは取り替えることも洗うこともできますし、スペアをお渡ししておけばお母さんが自分で取り替えることもできます。治療効果や赤ちゃんに対する負担、ご両親の使いやすさなど、いろいろなことを考慮して開発を進め、ここに行き着きました。これを更に改善しようという動きもどんどん出てきていますが、今の時点でも他と比べてとてもいいヘルメットだと判断しています。
小室:開発には自分も関わりましたが、五味先生が言われたように外国製のヘルメットはかなり硬く、重いですよね。ずっしりとして安心感はあるのかもしれませんが、クルムシリーズのようにこれだけ軽量で肌にも優しく治療効果が出るのであれば、やはりこちらの方がいいなと思います。十数年前、小児科医の同僚のお子さんが大学病院でヘルメット治療をやりましたが、その時は外国製のヘルメットを使っていたんですね。ですが頭皮とヘルメットが擦れてしまい徐々に髪の毛が生えなくなってしまったので、そこを切って縫ったと聞きました。それでも形が良くなって喜んでいたのを思い出します。このクルムシリーズは、少なくとも硬くはないので非常にいいのかなと。やはり国内の事情に併せて日本で作っている製品だと感じますし、今現在も改良を進めていると聞いているのでどんどん良くしていければと思っています。
──ヘルメットの重要性についてはどうお考えですか?

西巻:私は予防医療という意味でのヘルメット治療は非常に重要だと感じています。将来的に歪みに伴う身体の問題もありますし、整容面での悩みといった問題も出てくるでしょう。それらを予防する医療としての頭の歪みの矯正というのは重要なことです。当院の理念にもありますが、赤ちゃんの健やかな未来のために、予防医療としてのこのような治療は必要だと思いながら日々診療にあたっています。
大賀:治療とは別の話ですが、くびが座ってお座りして保育園に預けるようになると、お子さんは後ろに転んでゴツンと頭をぶつけることも多いですよね。そんな時に、クッションがこんな風にしっかりした形のヘルメットはまさに怪我の予防にもなるなと。そういう観点からも、ヘルメットは今後さらに受け入れられるようになるかもしれないのではと診療現場で思ってしまいました。
──0歳からの頭のかたちクリニックでは、ヘルメットがサイズアウトしてしまっても無料で作成する方針を取っています。なぜこのような取り組みを始められたのでしょうか。
西巻:比較的小さい月齢のうちに受診される方が増えてきていますが、小さい頭をスキャンして作成したヘルメットで治療を開始すると、2・3ヶ月で頭がぐっと成長することによりヘルメットが小さくなってしまうことがあります。ですがその時に「ヘルメットが小さくなったからもう治療を終了しよう」とはなかなか言えません。2個目を使うというのは赤ちゃんのためにはやはりベストな方法です。そのような理由から、無料で作成する方針を取るようになりました。以前より2個目を作るお子さんが増えてきましたね。
小室:より良い結果を求めるにはやはり治療を早く始めるのがベストで、3ヶ月で始めるのと4ヶ月で始めるのとでも全然違うんですよね。0歳からの頭のかたちクリニック福岡の梶田院長が執筆した論文によると、最重症のレベル4の場合、かなりの重症もいるので3ヶ月で始めても矯正の達成度合いは90%近くまで戻りますが平均するとわずかに90%に達しません。4ヶ月で始めた場合、その達成率はさらに下がってしまいます。小児科の先生方からは、首が座る前にやらない方が良いといったご意見もあるかと思いますが、形だけを考えると早く始めるのは非常に大事なことだと考えています。中にはすぐに治療に入らず、少し経過を見たいという親御さんもいますが、個人的にはそれは一番もったいないことだなと。一方で早く始めれば始めるほど頭の成長も早いのでヘルメットがどうしてもきつくなる可能性もあります。そのような背景があるので、結果にコミットするためには2個が必要ということを前提にしておくことも、ご家族が満足のいく結果を得るために必要な条件だと思っています。
大賀:効果の面で早くやることが重要だと思っています。ですが小児科デビューは、最初の予防接種が行われる生後2か月なんですね。そうすると、生まれてから最初100日までの一番大事な時に、基礎疾患もなく大丈夫だろうというところまで確認した上で、早く治療の効果を得るというのは必須です。くびが座っていない時期に、どうやってきちっと安全に3Dスキャンを撮るかはとても重要です。その時に稀な基礎疾患に少しでも配慮しているという状況は、ヘルメット治療においても安全性をより高めることにつながるのではないかと考えています。小児科医がゆっくり話を聞くこともできない多忙な中で、頭のかたちは放っておけば治るというような一言で片付けられてしまうと、お母さんたちの不安は解消しませんよね。私も反省しています。実際私たちのクリニックにも、「自然に治ると言われましたがやっぱり来ました」というお声が多く寄せられています。多忙な小児科の先生方をささえるためにも、0歳からの頭のかたちクリニックが存在できれば素晴らしいことだと思っています。そのように専門クリニックと連携しておくことで、小児科のかかりつけ医に予防接種や発達のことを聞かれた時も、お母さんの安心はまた全然違うものになるのではないでしょうか。
西巻:頭の形について不安に感じている親御さんが健診の時に相談しても、そこにいる医師は頭の形についての知識を持っていないことが多いのが実情です。ですから「放っておけば自然と丸くなりますよ」と言ってしまうかもしれません。ですがその先生は半年後にまた診てくれるわけでもなく、言ったら言いっぱなしなんです。そういった状況がおそらく今もまだ続いているので、親御さんたちの悩みはまだまだ解消できていないなと感じます。
──0歳からの頭のかたちクリニックでは、お子さんに対してレントゲン撮影を行っています。レントゲン撮影を行う目的や背景、安全面についても教えてください。

小室:レントゲンは、特に頭蓋縫合早期癒合症(注)ではないことを確認するという点では絶対に必要だと思っています。以前、ある小児病院の脳外科を受診したのちに当クリニックに来てレントゲンなしでヘルメットを始めた方がいらっしゃいました。医師からは「頭の形は異常なし」というお墨付きがあったので、余計な被曝を避けようということでヘルメット治療を始めたものの、まったく頭のかたちが良くなりません。結局治療を開始してから2ヶ月目にレントゲンを撮り、頭蓋縫合早期癒合症(注)が見つかって手術になった患者さんもいらっしゃいます。脳外科という専門家でもそういうことがありえるので、やはり客観的な評価としてレントゲン撮影による鑑別が必要だと考えています。 CTも低線量なタイプのものなら良いのかもしれませんが、それでもそれなりに被曝があります。現時点では、レントゲンが最も簡単で被曝もそれほど多くなくて良いと判断をしています。 (注)頭蓋縫合早期癒合症(ずがいほうごうそうきゆごうしょう)は、頭蓋において本来であれば離れているはずの2つの骨がくっついてしまっていたり、複数の骨がくっついて変形する病気。頭の形が不自然になったり、まれに脳の発達に影響が出たりすることがある病気。
五味:私もレントゲンは最低限必要だと思います。加えてエコー(超音波検査)も検討すべきだと思っています。欧米は放射線を嫌う傾向があり、アメリカのガイドラインなどには「なるべく画像検査をしないように」と書いてあります。ただエコーはやる人の技量にもよりますし、全体をエコーで見ていく必要があるので時間がかかります。もしかしたら、赤ちゃんにとってはかえって苦痛になる可能性もある。ですから身体への影響がほとんどない最小限の被曝量ですむレントゲンの方が有効な場合もあるのかもしれません。 ただし、レントゲン撮影を行っても見逃してしまう可能性は0ではありません。レントゲン撮影だけをすれば良いというものではなく、複数の専門家の目で見て確実な診断を行うということ必要だと思っています。その点、0歳からの頭のかたちクリニックには専門の医師が何人もいてダブルでチェックをすることを必須にしていますので、より見逃しも少なくなりますし、診断の精度も上がってくると考えています。
──3Dによる計測方法について詳しく教えてください。
小室:3Dスキャン撮影は、5方向から10個のカメラで一瞬で撮影し、それを解析します。耳の前の耳珠点と鼻根部を基準点として、体積や長さを測定しています。多少の誤差は出るかもしれませんが、かなり正確に評価ができると考えています。信頼度もありますし、それに基づいて適用を決めていくことに関しては合理性があると考えています。 改善度もはっきり数字化・見える化されているので、その辺りはご安心いただけるのではないかなと。私たちが主観で適当なことを言ってそれを患者さんに信じ込ませるわけではなく、客観的な数字で経過が見られる、かつその数字に基づき診療を医師が担当するので、そこは一番ご安心いただける点ではないでしょうか。
第1回: https://baby-helmet.com/?post_type=news&p=1138&preview=true
第2回:https://baby-helmet.com/?post_type=news&p=1140&preview=true
第4回:https://baby-helmet.com/?post_type=news&p=1142&preview=true